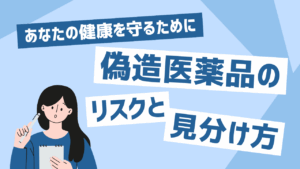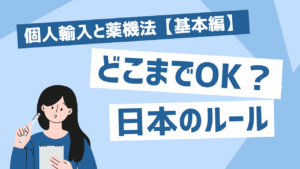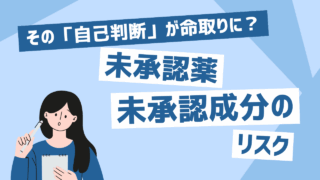
「薬剤師の海外医薬品相談室」ブログへようこそ! 前回は、個人輸入における深刻な問題の一つ「偽造医薬品」について詳しくお話ししました。
今回は、海外では広く使われていても、日本ではまだ承認されていない薬や成分が持つリスクについて深掘りしていきます。「海外で人気だから大丈夫だろう」「知り合いが使っているから安全」といった安易な判断が、実は大きな危険を招く可能性があるのです。
1. 未承認薬・未承認成分とは?
日本の医薬品は、厚生労働省の厳格な審査を経て、有効性、安全性、品質が確認されて初めて承認され、医療機関での処方や薬局での販売が許可されます。この審査は、臨床試験データなどに基づいて非常に慎重に行われます。
一方、未承認薬・未承認成分とは、以下のようなものを指します。
- 日本では承認されていない医薬品: 海外では広く流通している薬でも、日本ではまだ承認されていない、あるいは承認申請すらされていないケース。
- 日本で使われていない成分: 特定の成分が、日本では医薬品としても健康食品としても承認されていない、または使用が認められていないケース。
- 承認申請中の医薬品: 日本で承認されるための審査が進行中だが、まだ完了していない薬。
これらは決して「悪いもの」とは限りませんが、「日本の基準で安全性が確認されていない」という点が最も重要です。
2. 効果や安全性の情報が少ない
未承認薬・未承認成分の最大のリスクは、私たち日本人がアクセスできる信頼性の高い情報が極めて少ないことです。
- 日本語の詳しい添付文書がない: 正しい用法・用量、期待される効果、特に注意すべき副作用、他の薬との飲み合わせ(相互作用)などが詳細に書かれた日本語の文書がないため、適切な使用方法が分かりません。
- 情報源が不確か: ネット上の情報や体験談だけでは、その薬の全体像を正確に把握することは困難です。誤った情報や誇張された情報に惑わされる危険性があります。
- 個人の体質との相性: 日本人の体質に合わせた臨床データがない場合、海外では問題なくても、日本人には予期せぬ副作用や効果の出方が異なる可能性があります。
情報が少ない状態で使用することは、手探りで医療行為を行うようなものです。
3. 副作用が起こった場合の対応
もし未承認の薬や成分を使用して、体調に異変が起きた場合、その対応は非常に困難になります。
- 原因特定が難しい: 使用している薬が未承認であるため、医師や薬剤師が成分や作用機序を把握しにくく、適切な診断や治療に遅れが生じる可能性があります。
- 治療が複雑化: 日本で承認されている薬との相互作用で問題が生じた場合、その対処がさらに複雑になることも。
- 公的な救済制度の対象外: 万が一、重大な健康被害が発生しても、個人輸入による未承認薬の使用が原因である場合、医薬品副作用被害救済制度のような国の救済制度の対象外となることがほとんどです。
不安なときは
⚠️個人輸入は情報が出回りにくく、正確なことを調べるだけでも一苦労です。
そんなときはこちらから質問してください。あなたの疑問を解消できるかもしれません。
次回は、個人輸入を行う上で避けては通れない「薬機法」の基本について、分かりやすく解説します。どうぞお楽しみに!