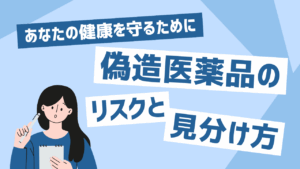「薬剤師の海外医薬品相談室」ブログへようこそ! 本日も、安全な個人輸入のために役立つ情報をお届けします。
個人輸入と聞くと、「安く手に入る」「日本では手に入らないものが買える」といったメリットを思い浮かべる方が多いかもしれませんね。確かに、個人輸入は非常に便利な側面を持っています。しかし、その便利さの裏には、知っておかないと危険な落とし穴が潜んでいるのも事実です。
今回は、個人輸入が「なぜ危険」と言われるのか、その根本的な原因についてお話しします。
1. 日本の基準と海外の基準は違う
私たちが普段、ドラッグストアや病院で手にする医薬品や健康食品は、日本の厳格な法律(薬機法など)に基づき、その品質、有効性、安全性が国によって確認されています。しかし、個人輸入で手に入れる海外の製品は、製造国の基準でしか管理されていません。
例えば、ある成分が日本では医薬品として扱われるのに、海外では健康食品として販売されているケースもあります。また、製造工程や品質管理の基準も国によって大きく異なり、必ずしも日本の高い水準が保証されているわけではありません。
この「基準の違い」が、まず最初の大きなリスクとなるのです。
2. 情報不足が招くリスク
海外の製品を購入する際、あなたはどんな情報を見ていますか? 多くの場合、簡単な商品説明やレビュー、あるいはSNSでの口コミが主な情報源ではないでしょうか。しかし、これだけでは製品の全容を把握することは非常に難しいのが現実です。
- 正確な成分表示がない:表示義務が緩い国の場合、すべての有効成分や添加物が明記されていないことがあります。
- 副作用や相互作用の情報不足:日本語の詳しい添付文書がないため、どのような副作用があるのか、他の薬との飲み合わせはどうか、といった重要な情報が見落とされがちです。
- 偽物・粗悪品の流通:インターネット上には残念ながら、偽物や粗悪品を販売する悪質な業者も存在します。見た目だけでは判別が難しく、情報が少ない中で本物と見分けるのは至難の業です。
これらの情報不足が、意図せぬ健康被害やトラブルにつながるリスクを高めます。
3. 「自己責任原則」の重み
個人輸入は、「個人の責任において輸入する」という原則に基づいて行われます。これはつまり、万が一、輸入した製品によって健康被害が生じたり、法律に違反する行為があったとしても、最終的な責任は全てあなた自身にあるということです。
日本の法律で守られているはずの消費者の権利や救済措置が、個人輸入の場合は適用されないことがほとんどです。何か問題が起きた際に、誰に相談していいのか、どこに責任を求めるべきなのかが不明確なため、全て自分で解決しなければならないという状況に陥りやすいのです。
まとめ:安全な個人輸入のために、まず「知る」こと
個人輸入は、使い方を誤ると大きなリスクを伴う可能性があります。今回お話しした「日本の基準との違い」「情報不足」「自己責任」という3つのポイントは、個人輸入を始める上で最も基本的な「なぜ危険なのか」という疑問への答えです。
これらのリスクを理解し、一歩踏み出す前に正しい知識を得ることが、あなたの個人輸入を安心・安全にするための第一歩となります。
不安なときは
⚠️個人輸入は情報が出回りにくく、正確なことを調べるだけでも一苦労です。
そんなときはこちらから質問してください。あなたの疑問を解消できるかもしれません。
次回は、個人輸入で特に注意が必要な「偽造医薬品」について、さらに詳しく掘り下げていきます。どうぞお楽しみに!